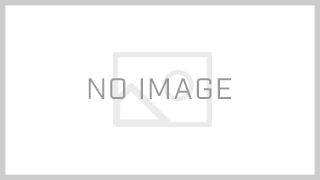はじめに
こんにちは。てくぞうです。
民間企業とはひと味違う世界。それが「官庁案件」です。
SIerとして初めて官庁案件に関わったとき、特に驚かされたのがドキュメント文化でした。
今回は、官公庁系プロジェクトで感じた「あるある」と、その中でどのように立ち回るとよいのか、SIer目線でお伝えします。
官庁案件でよくある「ドキュメント文化」5選
(1)A4数十ページが基本。とにかく文書量が多い
官庁案件では、設計書や報告書のボリュームがとにかく多いです。
- 基本設計書:100ページ超え
- テスト計画書・実施記録:詳細な手順+結果+証跡付き
- 仕様変更報告書:1項目でも3段構成で解説
見た目の整然さと、「何かあったときに責任を明確にする」ための文書化が重視されます。
(2)「形式」が命。書式・言い回しに厳しい
民間では多少ラフでも通る資料でも、官庁案件ではNG。
- 文言の表記統一
- ページ番号、目次、文書管理番号の明記
- 専用フォーマット厳守(Wordテンプレート多数)
など、形式美が非常に重要視されます。
書式チェックだけで数時間かかる…というのも、あるあるです。
(3)押印・紙文化が根強く残る
最近は電子化が進みつつありますが、まだまだ「印鑑文化」が根強い官庁案件も多いです。
- 納品物にすべて押印(電子データでもPDF化+押印ページ)
- 納品=紙+電子の両方が求められる
- 下版・確定済み書類は再提出不可
ドキュメント1つに「正式性」を持たせる文化が徹底されています。
(4)「読み手ファースト」での丁寧すぎる記述
官庁側の読み手は、必ずしもITの専門家とは限りません。
そのため、以下のような配慮が求められます。
- 専門用語は必ず補足説明
- 図解や表を多用して直感的に伝える
- 「前提条件」「目的」「影響範囲」などの見出しで段階的に説明
伝える力=品質の一部と捉えられている感覚です。
(5)レビューの回数とチェック体制が多段階
官庁案件では、1つのドキュメントが完成するまでに、複数階層のレビューが必要になります。
- 社内レビュー(複数回)
- 外部ベンダーとのレビュー
- 官庁担当者+その上の確認者チェック
結果、軽微な変更でも「再レビュー→再提出」の流れが必要になるため、スケジュールには余裕を持った管理が必須です。
SIerとして意識したいこと
納品物=「信用のかたまり」として扱う
官庁では、納品されたドキュメントがそのまま「品質評価の基準」になります。
だからこそ、納品物の品質がそのまま次の案件獲得に直結する可能性もあります。
- 誤字脱字1つでも信用を失うことがある
- 日付や版数管理は絶対にミスできない
- 「誰が読んでもわかる」資料づくりを徹底
こうした意識でドキュメントと向き合うことが重要です。
文書作成スキルは立派な「技術」
エンジニアというと技術や構築に目が向きがちですが、
官庁案件では「資料をきれいに作れる人」が非常に重宝されます。
- 要件をロジカルに整理できる
- 文章や図解で分かりやすく説明できる
- フォーマットへの対応が早い
これらも、立派な「技術力」として評価されます。
「報連相」と「記録」が命
官庁案件では、ドキュメントと一体で「透明性のある業務フロー」を作ることが求められます。
- 口頭で済ませない
- 変更点はメール・議事録で必ず残す
- 検討中・確定済みの区別を明確にする
「情報が残っていればトラブルにも強い」文化を、チーム全体で意識したいところです。
まとめ
官庁案件のドキュメント文化は以下のような特徴があります。
- 形式・正確性・分かりやすさに非常に厳しい
- レビューや承認のステップが多い
- 「資料づくり=成果物の中心」という認識が強い
SIerとして関わるうえでは、「書類作成=苦手な作業」ではなく、プロジェクトの要の1つと捉える意識が大切です。
丁寧に文書を整えることは結果的にチームの信頼と、次のステップにつながる大きな武器になります!