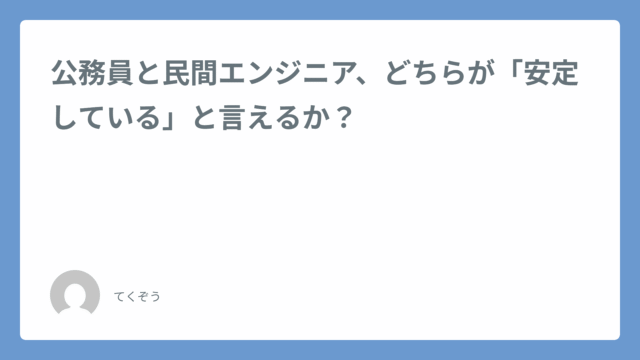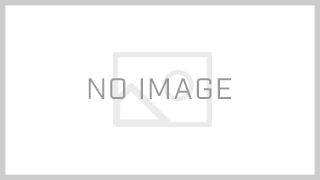はじめに
こんにちは。てくぞうです。
ITエンジニアを目指すうえで、避けて通れないのが技術書の読解です。
しかし、いざ手に取ってみると、
- 難しい言葉が多くて理解できない
- 分厚さに圧倒されて挫折する
- 途中で飽きてしまう
そんな悩みを抱える人も多いのではないでしょうか。
今回は、技術書を「読めない…」と感じる人に向けて、読む力を鍛える具体的なトレーニング方法をご紹介します。
なぜ技術書は読みにくいのか?
理由1:前提知識が不足している
技術書は、ある程度の前提知識があることを前提に書かれていることが多いです。
そのため、基本用語や概念が分かっていないと一気に理解が難しくなります。
例えば、
TCP/IPの話を読むには、ネットワークの基礎知識がないとついていけません。
理由2:抽象的な表現が多い
技術書では、概念的な説明や抽象度の高い言い回しが多用されます。
- 「この処理は非同期で実行されます」
- 「このモデルは責務分離の原則に則っています」
言葉だけだとイメージしにくく、モヤモヤしたまま読み進めてしまう原因になります。
理由3:最初から完璧を目指してしまう
技術書を読むときに、「一字一句理解しないといけない」と思い込むと、ちょっと分からないだけで手が止まってしまいます。
完璧主義が、結果的に読了までたどり着けない原因になりがちです。
読めるようになるためのトレーニング法
(1)最初から全部理解しようとしない
技術書は、1回読んで完璧に理解するものではありません。
まずは、
- 全体像をなんとなく掴む
- キーワードや重要ポイントだけ押さえる
ということを意識して、7〜8割理解できればOKくらいの気持ちで読み進めましょう。
(2)わからない単語は「飛ばして」読む
途中でわからない単語や用語が出てきても、いったん飛ばして先に進む勇気が必要です。
- 重要そうな単語だけメモしておく
- 後からまとめて調べる
このスタイルにするだけで、読書スピードが格段に上がります。
(3)実際に手を動かしながら読む
「読むだけ」で理解しようとするのではなく、実際にコードを書いたり、設定してみたりしながら進めるのが効果的です。
- サンプルコードを動かしてみる
- 図や表を書き写して整理する
体験を伴った読書のほうが、記憶に定着しやすくなります。
(4)アウトプット前提で読む
「読んだ内容を人に説明する」ことを前提に読むと、理解の深さが全く違ってきます。
- ブログにまとめる
- メモに要点を書く
- 誰かに教えるつもりで読む
アウトプットを意識するだけで、「自分が本当に理解できていない部分」が浮き彫りになります。
また、アウトプット前提で行うことで自分の理解も深まります。
詳しくはこちらの記事を参考にしてください。
「インプット大全」という本の書評をまとめた記事です。
アウトプットの大切さも研究の結果も用いて解説していますので、参考になると思います。
読むのにおすすめの技術書ジャンル
基礎系の技術書
最初は、できるだけ基礎を体系立ててまとめた技術書がおすすめです。
- ネットワーク超入門講座
- ゼロからわかるLinux入門
- はじめてのプログラミング(Python、Javaなど)
基礎ができれば、応用書にもチャレンジしやすくなります。
図解が多い本を選ぶ
文字ばかりの本よりも、図解やフローチャートが豊富な本を選ぶとイメージがつかみやすくなります。
最初は「薄め・図解多め」の本から始めて、徐々にステップアップしていきましょう。
まとめ
技術書が読めないと感じるのは、
「能力がないから」ではなく、正しい読み方を知らないだけです。
読む力を鍛えるためには、
- 最初から全部理解しようとしない
- わからないところは飛ばして進む
- 手を動かしながら読む
- アウトプット前提で学ぶ
この4つの意識を持つことが大切です。
最初は難しくても、繰り返していけば必ず読めるようになります。
焦らず一歩ずつ、読む力を育てていきましょう!