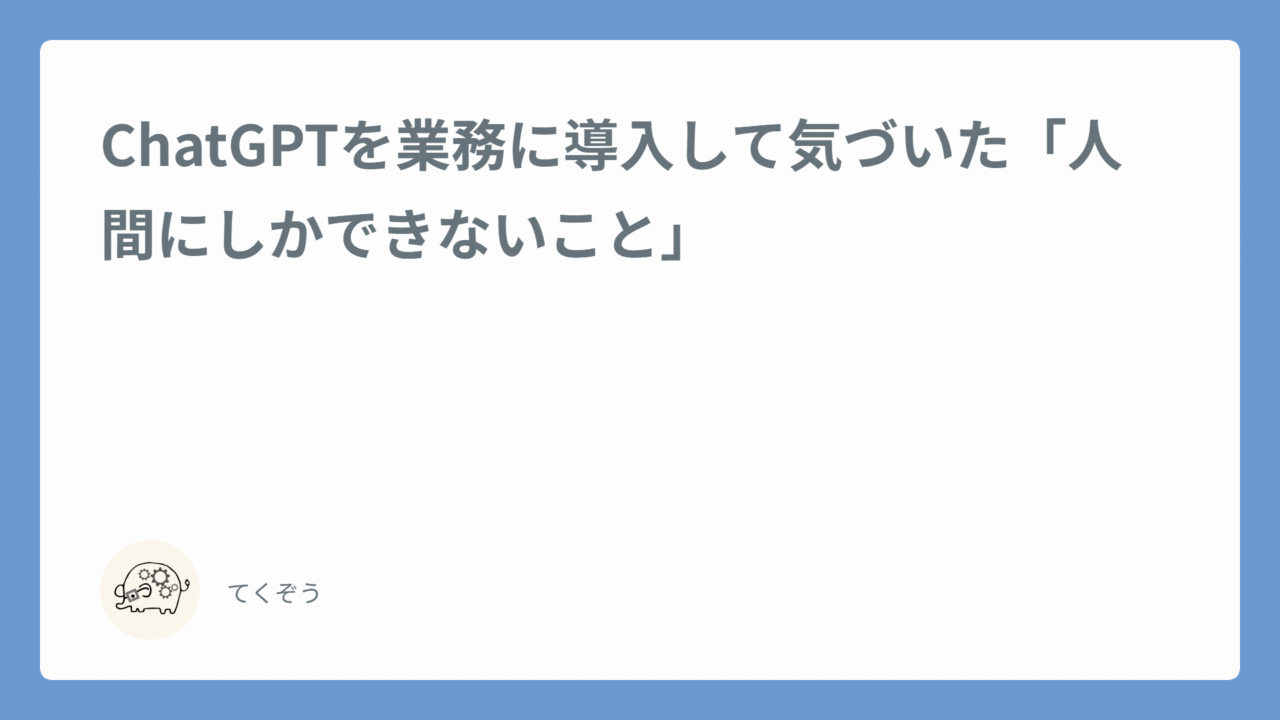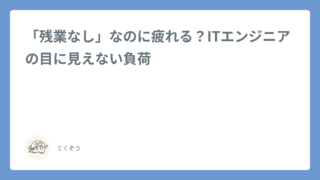こんにちは。てくぞうです。
ChatGPTを日常業務に取り入れる企業が増える中で、私もその波に乗ってAIを活用するようになりました。
議事録の要約、メール文面の作成、アイデアの壁打ちなど、あらゆる場面でAIは頼もしい相棒として活躍してくれます。
しかし、使いこなすうちに見えてきたのが、「結局、AIにはできないこともある」という現実。
この記事では、ChatGPTを導入した実体験をもとに、AIと人間の違い、そして人間にしかできないことについて整理してみたいと思います。
※本記事にはアフィリエイト広告を含みます。
1. 空気を読むことは、まだ人間の仕事
文脈だけじゃなく、感情や緊張感を察する
ChatGPTは論理的な文章を生成するのが得意ですが、たとえば以下のような場面では限界があります。
- 顧客との打ち合わせで「本音と建前」が入り混じる空気を読む
- 同僚の「ちょっとした表情や沈黙」から本心を察する
- 社内メールのニュアンスを、相手との関係性に応じて変える
こうした「非言語的な文脈」の解釈は、まだまだ人間の得意分野です。
2. 最終判断は人間がするしかない
「責任」はAIには持たせられない
ChatGPTは提案や選択肢を出すのは得意ですが、最終判断を任せることはできません。
たとえば、
- プロジェクトの方向性を決める
- 顧客対応で謝罪か交渉かを判断する
- トラブル発生時にどこに頭を下げるべきか考える
といった場面では、「責任を取る覚悟」が求められます。
AIは参考にはなっても、最終的な“決断”を下すのは人間であるべきです。
3. 「違和感」を拾えるのは、現場にいる人
データにないものを察知する直感
ChatGPTは大量のデータから「平均的な答え」を導くのが得意です。でも、現場で起きている微妙な違和感やズレには弱いです。
- 「なんとなく雰囲気がおかしい」
- 「この進め方、誰かが納得していない気がする」
- 「お客様の声はポジティブだけど、行動が伴ってない」
こうした“感覚のズレ”をキャッチできるのは、人間が現場で直接やり取りしているからこそです。
4. アイデアの本当の種は“雑談”から生まれる
余白や無駄の中にこそ創造性がある
ChatGPTは質問すれば必ず何か答えてくれますが、「雑談から自然に発展するアイデア」はまだ生み出せません。
- ランチ中の何気ない話題
- 他愛もない愚痴
- 趣味や関心から話が広がる会話
こうした偶発的なコミュニケーションが、新しい企画や改善案のヒントになることは少なくありません。
AIとのやりとりには、まだこの“余白”がありません。
5. 「人間らしさ」こそがAI時代の価値になる
ChatGPTはあくまで「補助ツール」です。仕事の一部を肩代わりしてくれる強力な相棒ではありますが、“人間らしさ”を完全に再現することはできません。
だからこそ、これからの時代に必要なのは、
- 感情を理解する力
- 空気を読む力
- 「違和感」に気づく感性
- 自分の言葉で話す力
- 判断して責任を引き受ける覚悟
といった人間にしかできない領域を伸ばすことなのです。
まとめ
ChatGPTの導入によって、業務効率は確実に上がりました。
しかし、だからこそ気づいたのが、「人間にしかできない仕事」が明確に存在しているという事実です。
- AIは“言葉”を作れるが、“気持ち”は伝えられない
- AIは“選択肢”を出せるが、“決断”はできない
- AIは“正解”を導けるが、“共感”はできない
AIと人間が協働していくこれからの時代、私たち人間が持つ“らしさ”をどう活かすかがより重要になってくるはずです。
どうせAIに置き換わるなら…ではなく、「AIがあるからこそ自分の価値を見直す」という視点で、働き方を見つめ直してみてはいかがでしょうか?