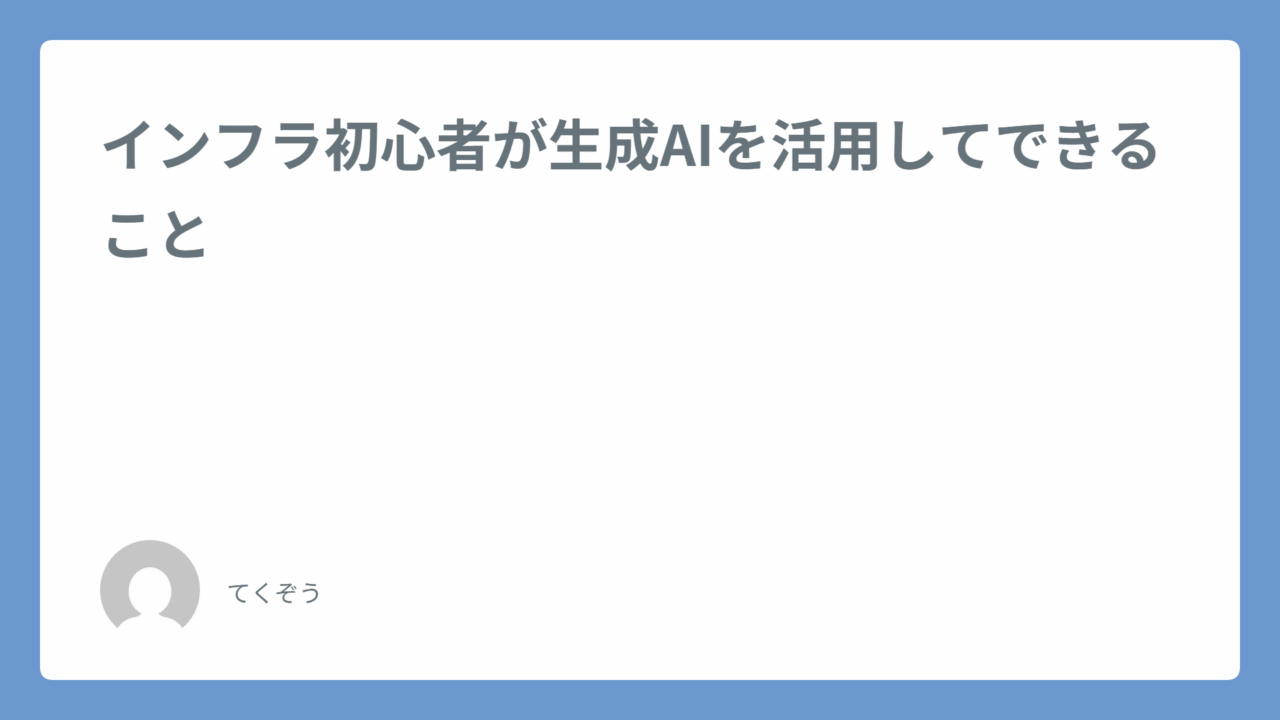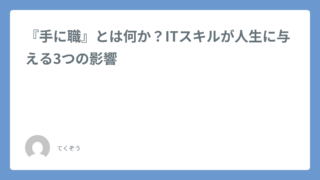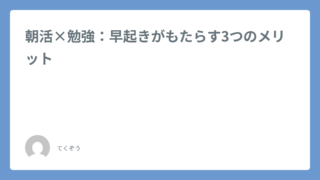はじめに
こんにちは。てくぞうです。
エンジニア1年目やインフラ初心者にとって、日々の学習や業務はまさに未知との遭遇。
「このコマンド何だっけ?」「ネットワークの仕組みが難しい…」「ドキュメントの書き方が分からない」
そんな悩みを、生成AIが解決の糸口をくれるかもしれません。
今回は、私自身が生成AIを活用してインフラ知識を深めた経験を交えながら、AIとの学びの相性や活用法をご紹介します。
※本記事にはアフィリエイト広告を含みます。
インフラ学習こそ、生成AIが役立つ理由
インフラの学習では「基礎概念」「コマンド」「設定ファイル」「ネットワーク構成」など、抽象的かつ広範な知識が求められます。
そんな中で、生成AIが特に役立ったと感じた理由は以下の3つです。
- 質問のハードルが低い:
何度聞いても怒られないので、「これは初歩的すぎるかな?」という質問も気軽にできる - 用語の意味をかみ砕いてくれる:
LinuxやTCP/IPなどの専門用語も、初心者向けにわかりやすく変換してくれる - 複雑な設定をシンプルに要約:
設定ファイルや手順をコード付きで説明してくれるので、実務にもつながりやすい
生成AIで実際にやってみた活用例
1. コマンドの意味をその場で解説してもらう
sudo lsof -i -n -P
こういった複雑なコマンドも、ChatGPTに貼り付けて「これは何をしているの?」と聞くだけで、各オプションの意味まで丁寧に解説してくれます。
2. ネットワーク構成の理解を図解で助けてもらう
「VLANってどうなってるの?」といったネットワークの概念も、図解のような説明をお願いすると、イメージしやすい文章に変換してくれます。
3. トラブル対応のシナリオ練習
「pingが通らない時、何から調べればいい?」というような質問をすると、優先順位付きで対処ステップを提示してくれました。
実際の現場でも役立つ思考トレーニングになります。
注意点:生成AIは「教科書の代わり」ではない
生成AIは便利なツールですが、「全てを鵜呑みにしない」ことが大切です。
とくに設定ファイルの内容や最新技術については、公式ドキュメントで裏取りをするクセをつけましょう。
また、「なぜそうなるのか?」を自分でも考える習慣がないと、“ただの丸暗記”になりやすいです。
生成AIは“先生”というよりは、優秀な補助輪と考えると良いかもしれません。
まとめ:AIと一緒に成長する時代へ
インフラエンジニアの世界は日々進化しています。
そんな時代に学ぶ私たちには、AIという最強の学習パートナーがいます。
学び方も、働き方も、どんどん変わっていく中で、「AIをどう使うか?」という視点も、今後のキャリア形成において大切なスキルになるはずです。