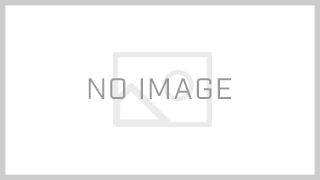はじめに
こんにちは。てくぞうです。
「文系だからエンジニアには向いていないのでは…」
そんな不安を抱えながらIT業界に飛び込んだ方も少なくないと思います。
私も文系出身としてエンジニアになりましたが、
「苦手なところを補う」だけでなく、
「文系ならではの強みを活かす」ことが、結果的に武器になってきました。
今回は、実際に私が行ってきた工夫や考え方をご紹介します。
文系出身でも活かせる「得意」とは?
(1)言葉をわかりやすく伝える力
教育学部出身ということもあり、以下のような「伝える力」は自分の強みだと感じています。
- 難しい内容をかみ砕いて説明する
- 相手に応じた言い換えができる
という
このスキルは現場のあらゆる場面で活かせています。
たとえば、
- チーム内での技術共有
- お客様への提案や報告
- マニュアルや手順書の作成
など
(2)相手の立場で考える姿勢
公務員時代に培った「住民目線で考える力」も、IT業界で非常に役立ちました。
たとえば、
- 技術者目線ではなく、ユーザー目線でUIや仕様を考える
- クライアントの業務背景を汲み取って提案内容を調整する
このような場面では、論理性よりも共感力や想像力が求められることも多いです。
(3)文章や資料を整える力
文系の学びで培った「読み書きの基礎力」は、エンジニアとしてのアウトプットの質に直結します。
- 設計書の構成を分かりやすく整理する
- 社内向けの資料を読みやすくレイアウトする
- 日報や報告書で適切に要点をまとめる
こうした場面で「読みやすい文章」が書けることは、大きな信頼にもつながります。
得意を活かすために意識したこと
(1)あえて「説明役」を買って出る
「自分は技術面ではまだ未熟」と感じていた時期、私はチーム内で「説明担当」や「まとめ役」を積極的に引き受けました。
- 新人向けにツールの使い方を説明
- 会議後の議事録をわかりやすく整理
- 手順書の作成やマニュアル整備
こうした役割は、文系出身の自分にとって得意分野でしたし、周囲からも信頼される機会が増えていきました。
(2)「わからない視点」をあえて大事にする
技術に詳しい人ほど、「前提知識がある人向け」に話しがちです。
だからこそ、自分が初心者だった経験を活かして、以下の行動を起こしました。
- 「ここが分かりづらかった」とフィードバックする
- 「自分ならこう説明する」という代案を出す
このような行動が、「視点の違い」として重宝されることもあります。
(3)技術は後から身につければOKと割り切る
もちろん、技術を学ぶ努力は欠かせません。
でも、最初から全部できる必要はないと割り切りました。
むしろ、
- 自分の強み(言語化・説明・気配り)を活かしつつ
- 徐々に技術領域を広げていく
この順番が、私には合っていたと思います。
まとめ
文系出身でも、エンジニアとして活躍することは十分に可能です。
大切なのは以下のような点です。
- 技術だけにこだわらず、自分の得意を見つめ直すこと
- 「説明力」「共感力」「文章力」といった文系スキルを活かす場面を探すこと
- 自信が持てなくても、一つひとつ経験を積み重ねること
「文系だから不利」と思うのではなく、「文系だからできること」に目を向けていきましょう。
必ず、自分ならではの強みが武器になります!