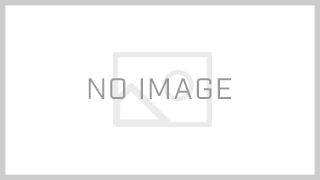はじめに
こんにちは。てくぞうです。
ITエンジニアとして転職や就職を考えるとき、求人票やエージェントから「SES」「受託開発」「自社開発」といった用語を目にすることがあるかと思います。
これらはどういった働き方や契約形態を指すのか、また、それぞれにどんなメリット・デメリットがあるのか理解しておくと、自分に合ったキャリアを見つける上で非常に有益です。
今回は、それぞれの特徴と選び方のポイントをご紹介します。
1. SES(システムエンジニアリングサービス)とは
(1) 具体的な働き方
- 契約形態:
エンジニア本人はSES企業に所属しつつ、クライアント先(常駐先)に派遣されて業務を行う形態。 - 業務内容:
Web開発、インフラ構築、運用保守などクライアントのプロジェクトによって多種多様。 - 期間:
プロジェクト単位で数ヶ月~1年以上と幅広い。
(2) メリット
- 多種多様な現場を経験できる
短期間でいろいろな技術や業務プロセスを知ることができ、スキルの幅を広げやすい。 - 未経験OK求人が比較的多い
エンジニア育成に力を入れているSES企業もあるため、異業種からの転職もしやすい場合がある。
(3) デメリット
- 配属先や業務内容のコントロールが難しい
クライアントの要望次第で、業務範囲や勤務地が変わることがある。 - 自社社員同士の連携が薄くなる可能性
常駐先で働くため、所属企業の仲間と直接交流する機会が少ない。
2. 受託開発(受託・請負)とは
(1) 具体的な働き方
- 契約形態:
受託企業がクライアントから開発案件を「請け負う」形。
エンジニアは基本的に自社オフィスや在宅で作業し、クライアントと要件を詰めつつシステムを完成させる。 - 業務内容:
要件定義、設計、実装、テスト、納品まで一貫して担当する場合が多い。
プロジェクトごとに内容や規模は様々。
(2) メリット
- プロジェクト単位のスキルが身につく
要件定義から納品まで、ソフトウェア開発の全工程を経験できるケースが多い。 - 自社で完結するため、チームワークが活発
同じ会社内でチームを組みやすく、ノウハウの共有やレビューなどがしやすい。
(3) デメリット
- 納期や要件変更のプレッシャー
「納品までに仕上げる」という契約ゆえに、納期に追われたり、スコープ変更が発生すると負荷が高くなりやすい。 - 終わればプロジェクト終了
納品後の運用や追加開発が入らなければ、そこで案件は完了。
安定した収益源を得るには新規受注が必要となるため、会社の受注状況に左右される。
3. 自社開発(自社サービス)とは
(1) 具体的な働き方
- 契約形態:
自社サービスや自社プロダクト(Webアプリ、スマホアプリなど)を開発・運用する企業に所属し、社内でサービスを育てていく。 - 業務内容:
企画、開発、テスト、運用、改善まで幅広く関わることが多い。
ユーザーの反応やビジネス面を考慮しながら機能追加や改修を行う。
(2) メリット
- 長期的な視点で開発できる
自社製品のため、納期第一というよりユーザーやビジネスの成長を考慮しながら開発するケースが多い。 - やりがいと愛着が生まれやすい
自分が手がけた機能がユーザーに使われる喜びをダイレクトに感じることができる。
(3) デメリット
- 技術スタックが限定される場合も
会社やプロダクトによって使う技術が固定化されていると、新しいスキルを身につけにくいことがある。 - 急成長・急展開に対応する覚悟
自社開発企業はベンチャーやスタートアップが多く、事業環境の変化に合わせて大幅な方針転換や仕様変更が発生する可能性が高い。
4. 選び方のポイント
- 学びたい技術・スキルの方向性
- 幅広い経験を積みたい → SESや受託開発で多様なプロジェクトに触れる
- 特定の分野を深堀りしたい → 自社開発や専門性の高い受託案件が向いている
- 働き方のスタイル
- いろんな現場を渡り歩きたい → SES
- 基本は社内で開発していたい → 受託開発・自社開発
- ユーザーに直接価値を届けたい → 自社サービス
- キャリアビジョンややりがい
- 上流工程やマネジメントを目指したい → 受託開発で要件定義~納品までを経験、または自社開発でプロダクト全体に関与
- サービス開発で愛着を持ちたい → 自社開発企業
- コミュニケーション力を磨きたい → SESや受託でクライアントとの折衝が多い現場
- 会社の規模・体制
- 大手SESや大手受託は教育体制が充実していることが多い。
- ベンチャーの自社開発では裁量が大きく、スピード感を求められる代わりに成長のチャンスが大きい。
5. 実際に働く前にできること
- 面接や説明会で現場のリアルを聞く
- SESなら「配属先はどうやって決まる?」「希望をどれだけ考慮してもらえる?」
- 受託なら「一つのプロジェクトはどれくらいの期間?」「開発プロセスやツールは?」
- 自社開発なら「自社サービスの開発方針や技術スタックは?」「開発の自由度は?」
- 転職エージェントに相談
- それぞれの企業がどの形態を中心に行っているか、どんな現場環境かを教えてもらえる。
- 「SESと受託を両方やっている」ハイブリッド企業もあるため、詳しく質問してみる。
- SNSやコミュニティで情報収集
- TwitterやQiita、Zennなどでエンジニアの生の声をチェック。
- 実際にSES・受託・自社のいずれかで働くエンジニアがどんな感想を持っているのか参考にすると具体的なイメージが湧きやすい。
まとめ
「SES」「受託開発」「自社開発」とひとくちに言っても、企業やプロジェクトごとに働き方は大きく異なります。
自分がどんなスキルを身につけたいのか、どのような環境でモチベーションが上がるのかを考えながら、複数の企業や求人を比較検討するのがおすすめです。
- SES: 多種多様な現場に行きやすく、幅広い経験ができるが、配属先の自由度は低い。
- 受託開発: プロジェクト完結型で、開発工程全体を学びやすいが、納期や要件変更のプレッシャーが大きい。
- 自社開発: 自社サービスを育てるやりがいがあり、長期的視点の開発ができるが、技術選択や方針転換のリスクに左右される。
最適解は人によって違います。
まずはご自身のキャリアビジョンを明確にし、そのうえで企業や現場のリアルを収集してみてください。
きっと、自分に合ったエンジニアライフが見つかるはずです。
最後に
SES・受託・自社開発のいずれの形態も、一概に「どれが良い悪い」というわけではありません。
会社やプロジェクト、業務内容、チーム体制などによって実情はさまざまです。
この記事を参考に、自分の性格やライフスタイル、将来の目標を踏まえながら、最適な環境を探してみてください。